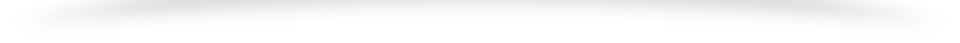生物は暗記の特色が強い
生物は理科の一つの科目ですが、物理や化学と異なり、暗記の度合いが強い科目です。
必要なことを覚えることができればそれだけで特典を伸ばすことができるようになるので、しっかりと覚えていくことが大切です。
また、それに加えて遺伝などでは計算も必要になるので、合わせてマスターしていきましょう。
計算と言っても数学のように複雑な問題が出題されるわけではなく、原理が理解できていればきちんと解くことができます。
慣れが必要になる分野でもあるので、問題数を当たって理解を深めておくことをおすすめします。
生物は文系の方でも選択する方も多い科目ですが、必要なことを覚えることで得点源にすることができます。
ぜひマスターしていくことをおすすめします。
生物は分野間のつながりが薄め
物理や化学の場合、一つの分野の知識や考え方が他の単元にも繋がっていることが多いです。
物理ではエネルギーの考え方などは電気や熱などの分野でも使いますし、化学も同じようにモルの計算方法などは有機化学でも無機化学でも使います。
ですが、生物ではひとつの単元が独立していることも多いため、比較的どの分野からでも勉強しやすくなっています。
生物の勉強をこれから始めるという方の場合は、まずは取り組みやすい分野から取り組んでみるのもおすすめです。
そこから学習に慣れてきたら他の分野を進めていくのもスムーズになり、さらに定着のスピードも上がっていきます。
生物は暗記が大切になりますが、参考書などでは暗記しやすいようなシートが付いていたり、まとめのページがあるものも多いです。
これを活用しても良いですし、自分なりにまとめたページを作ると理解を深めながら今後の暗記に活用することができます。
気を付けたいのはノートを作ることが目的にならないようにするということです。
ノートは作った後に活用することで意味が出てきます。
せっかく手間をかけて作るものなので、今後の勉強に役立てることを念頭に置いて作っていきましょう。
記述の問題への対策も必要
生物でもうひとつ慣れておきたいのが記述式の問題への対応です。
国公立大学の二次試験では生物は記述式の問題が出題されることも多いです。
普段から記述に慣れていないと回答できない問題も多いですし、単に用語を暗記するだけでなく流れを理解しておく必要もあるので、ぜひ日頃から慣れておきましょう。
もちろんセンター試験までで良い方や私立大学でマーク式でしか出題されない大学を受験する場合は必要ありません。
志望校の過去問を早めにチェックして、必要かどうかを早い段階で見極めると良いでしょう。
以上が生物の勉強法になります。
きちんとポイントを押さえて勉強を進めれば、文系の方でも得点源にしやすい科目なので、力を入れて勉強してみるのもおすすめです。