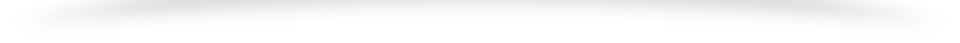効率のいい勉強方法とは
効率のいい勉強方法がわかれば、効率よく勉強をして集中させるといいですね。
勉強時間は効率的でなければレベルが高い学習にはなりません。
そのレベルの高い学習を積み重ねることで成績も上がりますし、偏差値も上げることができます。
最終的に目標を達成させるためにも効率のいい勉強方法を身につけましょう。
長時間勉強していてもそれは空回りで意味がありません。
勉強をする時間の長さが重要なのではなくて時間が短かったとしても、いかに効率よく勉強しているかが重要です。
それでは効率よく勉強するためにはどうすればいいのでしょうか。
時間を区切る
最初に、時間は短く設定して区切りましょう。
長時間だらだら勉強していてもいけません。
長時間学習するのではなくて、くぎりましょう。
1年の単位で見る場合も1ヶ月や1週間で区切り、そして1日の勉強時間も細かく区切ってモチベーションを高めたほうがいいでしょう。
1時間半で設定するのが一番効率がいいといわれています。
1時間半でちょうど脳が疲れてくるころなので、脳の疲れも解消されますしリフレッシュさせるのにも効果的です。
そして休憩を上手に取り入れましょう。
3時間から7時間休まずに勉強をしている人がいたとしても、これは効率がいい勉強をしているとはいえないのです。
筋肉は凝り固まりますし、血液の流れも悪くなります。
脳に血液が回らなくなれば脳の回転も悪くなります。
ですから1時間から1時間半に1回は休憩を挟むことで脳もリセットされますので、効果的な勉強につながります。
効率が下がる原因の1つに眼精疲労がありますから、目が疲れたと思ったら少し休むのも効率を上げるためには大切です。
違う種類を組み合わせる
そして種類が違う種類の科目を組み合わせることも大事です。
勉強時間を効率よくさせるためには、いつも新鮮さを考えることが大事です。
どうしても脳は単調なことを繰り返すとボーっとしてきますし、眠気を引き出しますので、常に新鮮な刺激を与えているとボーっとすることも眠気もないのです。
勉強をする際、ずっと座りながらではなくて動きながら勉強をすることも大事です。
動きながら勉強すれば頭が働きやすい傾向にありますので、少し体を動かして見るなど工夫するといいでしょう。
人間は動物で、動物はもともと動き回って生活する生き物ですので、じっとしているよりも動き回っているほうが脳の働きがいいのです。
ですから動き回って体を動かして脳を活性化させることも大事です。
効率よく勉強させるために適度にストレッチなども加えていきましょう。