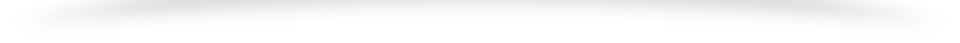大学受験の仕組み、実はあまりよくわかっていない
大学受験をこれから経験するという人の中には、大学受験の事について実はよくわかっていないという人が多いです。
例えばAO入試っていうのはどういう入試なのか、推薦入試と何が違うのか、又国公立と私立大大学では試験の方法ってどう変わるの?前期、中期、後期って何?とわからないことの方が多いという人もいるでしょう。
入試の種類は3つに分かれる
大学の入試は大きく3つに分けることができます。
まず一般入試、これは学力一発勝負という入試で、今多くなっている推薦入試とは違い、大学受験ではメインとなる選抜方式です。
基本として英語、数学、国語の主要科目の筆記試験、マークシート試験があります。
推薦入試とAO入試は一般入試の前に行われている人柄重視の試験です。
高校の評定、書類審査、面接、小論文などで学力以外の部分でも、総合して受験生を審査する方法です。
推薦入試は指定校推薦と公募推薦があり、いずれも高校の推薦状がないと受験する事が出来ない方法です。
指定校推薦を受験する場合、本当に何か間違ったことをしない限り100%合格です。
公募の場合高校の推薦基準と大学の出願条件を満たすことで応募できます。
AO入試はアドミッションズ・オフィスという略で、出願者の人物像を学校側が求めている学生像と照らしあわせてみて、その上で合否を決定するという方法です。
大学が欲しいと思う学生を選抜するという方法なので、高校の推薦状が必要なく、大学に入りたいという熱意を見ます。
書類審査、面接、受験生の個性などを確認し評価され、実施校も多いですが数としては横ばいです。

人物重視だからこそ、その大学で自分が何を学びたいのか、将来どのような目標を持っているかなど、明確な軸を持って挑むようにしましょう。
国公立の入試はどうなっているのか
国公立大学は独立行政法人大学入試センター作成の試験を受ける必要があり、これをセンター試験という一次試験として受けます。
国公立大学を志望する受験生全員が1月に試験を受けることになります。
全ての受験生が同じ問題を解くことになるので、これによって成績が明らかになります。
センター試験の自己採点による得点率で、次の二次試験を受ける大学を決めます。
センター試験の翌日、自己採点を行いその採点によって、志望校のボーダーラインと照らし合わせ、どの学校受験するかを決めていきます。
センター試験はほぼすべての国立大学は5科目7教科で、つまりすべての科目に対策が必要となり、通常高校1年、2年からしっかりと向き合った対策が必要となります。
センター試験後、国立の場合は2月上旬に出願しますが、日程が統一されているので1つの大学以外受験できません。
第一志望は前期で、第2志望は後期に受験するというのが一般的なようです。
前期で合格し入学手続きを行うと中期、後期は受験しても合格できません。
私立大学については、何校も併願することができ、受験する大学によって受験科目も違ってきます。
ただ最近センター利用の学校が多くなり、この場合、センターの受験科目を利用し複数の大学を受けることができ便利な方法とされています。