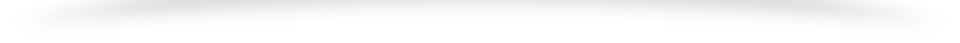勉強できる子出来ない子、どんな差があるのだろう?
小学校までは成績もよくて何も心配することがなかった、でも、中学校に上がったらいきなり成績が落ちて・・・という親御さん、よくこの話を聞きます。
いついつまではよかった、でもその後、全く駄目になってしまった、これはテストの点数などを比較し、小学校と中学で違うという比較をしているのだと思います。
勉強が出来なくなったのではなく、教師から見ると勉強の内容が難しくなり思考力、問題解決力などのその生徒自身の能力が勉強に追いつけなくなったという事が正解なのだそうです。
中学校では同じくらいの成績だったのに、高校になると一人は偏差値70、一人は偏差値40、一体この差はどこで生まれてしまったのでしょうか。
中学の時には同じくらいの成績だったのに差が付いた、また勉強量は偏差値が低い方の子が勝っているのにどうして?と思うことも少なくないでしょう。
保護者の方からすると、こうしたことを受け入れることが出来ないのですが、どうしてなのかという事を保護者もお子さんもしっかり考えた方がいいのです。
本質を見分ける力を得ることが大切
中学校では同じ成績、でも高校にいって格差出来てしまったという場合、この差は勉強量によるものではなく、生徒そのものがもっている力に元々差があったからです。
同じ中学出身、中学では自分の方が成績もよかったのに、勉強量の少ないあいつの方がどうして成績がいいのだろう?こういう気持ちを持ってしまうのもよくわかります。
努力している自分が負けて、努力していない相手が勝つ、これはつらい事です。
でもここで気が付いたという事は大きなチャンス、どうして努力している自分が負けてしまうのか?という事を考えることができます。
中学まで成績がよくてその後下がっていくという生徒は、勉強のパターンで覚えようとしていて、どういう風に解けばいいのか?という自分で考える力が身についていないだけなのです。
これまでの勉強法を見直すことで高校になってから行うべき学習法がわかってきます。
勉強の土台作りをすることが大切
今は定期テストよりも、土台をつくるという事が必要です。
中学の時に本当はわからない部分があったはず、そこを点数がいいからと見逃していたのかもしれません。
高校の勉強をしながら、もう一度中学のおさらいをしてみると、あれ?これはどういう風に解くんだっけ?とわからない部分が出てくると思います。
そこを、今、高校に上がってくすぐならもう一度おさらいし、土台をつくっていくことができます。
目先の勉強よりも、今すべきこと、出来ないことを出来るようにすることが本当に意味がある勉強、知識をつける勉強に必要な事です。